子どもの成長期に「身長をもっと伸ばしたい」と願う親御さんは多いでしょう。牛乳やカルシウムが身長に大切とよく言われますが、実は見逃されがちな栄養素があります。それが「亜鉛」です。
亜鉛は体のさまざまな機能に関わる必須ミネラルで、特に成長期の子どもにとっては身長の伸びに直結するカギとなる栄養素です。この記事では、亜鉛と身長の関係、不足によるリスク、そして日常の食事での効果的な補い方について詳しく解説します。
亜鉛と身長の関係とは?
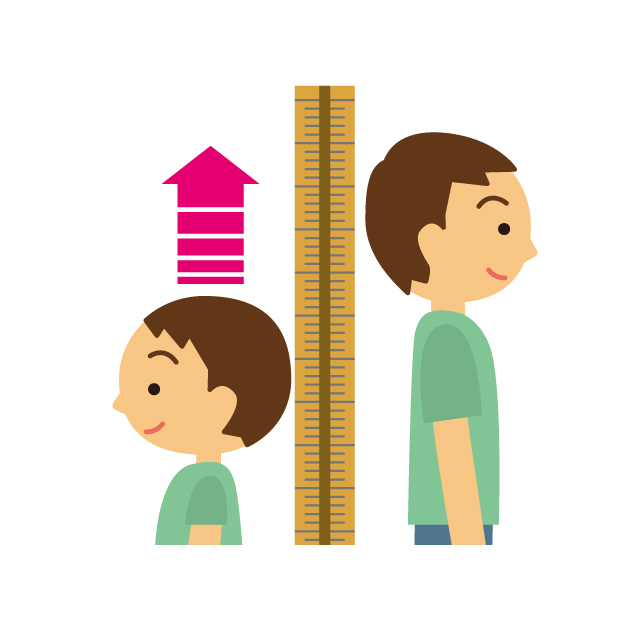
亜鉛が成長ホルモンに与える影響
身長の伸びには「成長ホルモン」が欠かせません。このホルモンが骨の成長板に働きかけ、骨を長く伸ばすことで身長が高くなります。
ここで重要なのが、成長ホルモンの合成に亜鉛が深く関わっているという点です。亜鉛が不足すると、いくら成長ホルモンが分泌されても十分に働けず、結果として骨の伸びが妨げられてしまいます。
骨や筋肉の発育に欠かせない理由
亜鉛はタンパク質の合成にも必須です。骨や筋肉はタンパク質を土台として作られるため、亜鉛不足は体全体の発育に悪影響を及ぼします。
また、骨密度を高めるカルシウムやビタミンDを効率よく働かせるためにも、亜鉛の存在は欠かせません。
子どもに必要な1日の亜鉛摂取量
厚生労働省が定める「日本人の食事摂取基準(2025年版)」によると、子どもの亜鉛推奨量は以下の通りです。
- 6〜7歳:5〜6mg
- 10〜11歳:7〜8mg
- 12〜14歳男子:9〜10mg、女子:8mg
実際には、成長期の子どもは食欲のムラや好き嫌いで不足しやすいのが現状です。
亜鉛不足で起こる成長への影響
身長が伸びにくくなるメカニズム
亜鉛不足になると成長ホルモンの働きが鈍くなり、骨の成長板の細胞分裂が低下します。その結果、身長の伸びが止まりやすくなります。
免疫力・集中力の低下にもつながる
亜鉛は免疫細胞の働きや神経伝達物質の合成にも関わっています。亜鉛不足が続くと、風邪をひきやすくなったり、集中力が低下して学習面にも影響が出ることがあります。
見逃しやすい亜鉛不足のサイン
- 爪に白い点が出る
- 食欲不振
- 味覚の低下(味が分かりにくい)
- 傷が治りにくい
こうしたサインが見られる場合、成長面だけでなく健康全般に影響している可能性があります。
亜鉛を多く含む食品リスト
子どもにおすすめの食材
- 牡蠣:亜鉛含有量は食品中トップ。
- 牛肉(赤身):吸収率が高く、成長期に最適。
- 卵黄:手軽に摂れる栄養源。
- 小魚・イワシ:カルシウムと同時に摂れる。
- 納豆・豆腐:植物性食品の中では比較的豊富。

吸収率を高める食べ合わせ
亜鉛は単体では吸収されにくいため、動物性たんぱく質(肉・魚)やビタミンCと一緒に摂ると吸収率が上がります。
例:牛肉のステーキ+サラダ、牡蠣フライ+レモン
逆に亜鉛吸収を妨げる食品
インスタント食品やスナック菓子に多いリン酸塩や、穀物に含まれるフィチン酸は亜鉛の吸収を妨げます。主食を精製度の高い白米やパンだけに偏らせず、バランスの良い食事を心がけましょう。
食生活で不足を補う工夫
毎日の食卓に取り入れやすいメニュー例
- 牛肉入りチャーハン
- 牡蠣の味噌汁
- サバの塩焼き
- 卵とほうれん草の炒め物
特別な食材を買わなくても、普段の料理に意識的に取り入れるだけで効果があります。
好き嫌いが多い子どもへの工夫
魚や牡蠣が苦手な場合は、ひき肉を使った料理(ハンバーグ、そぼろ丼)が食べやすいでしょう。また、ふりかけやごま和えで小魚や海藻を取り入れるのもおすすめです。
サプリメントを活用する際の注意点
サプリメントで補うのも一つの方法ですが、過剰摂取は吐き気や下痢、銅の吸収障害を引き起こす可能性があります。必ず用法・用量を守りましょう。
身長を伸ばすために大切な生活習慣
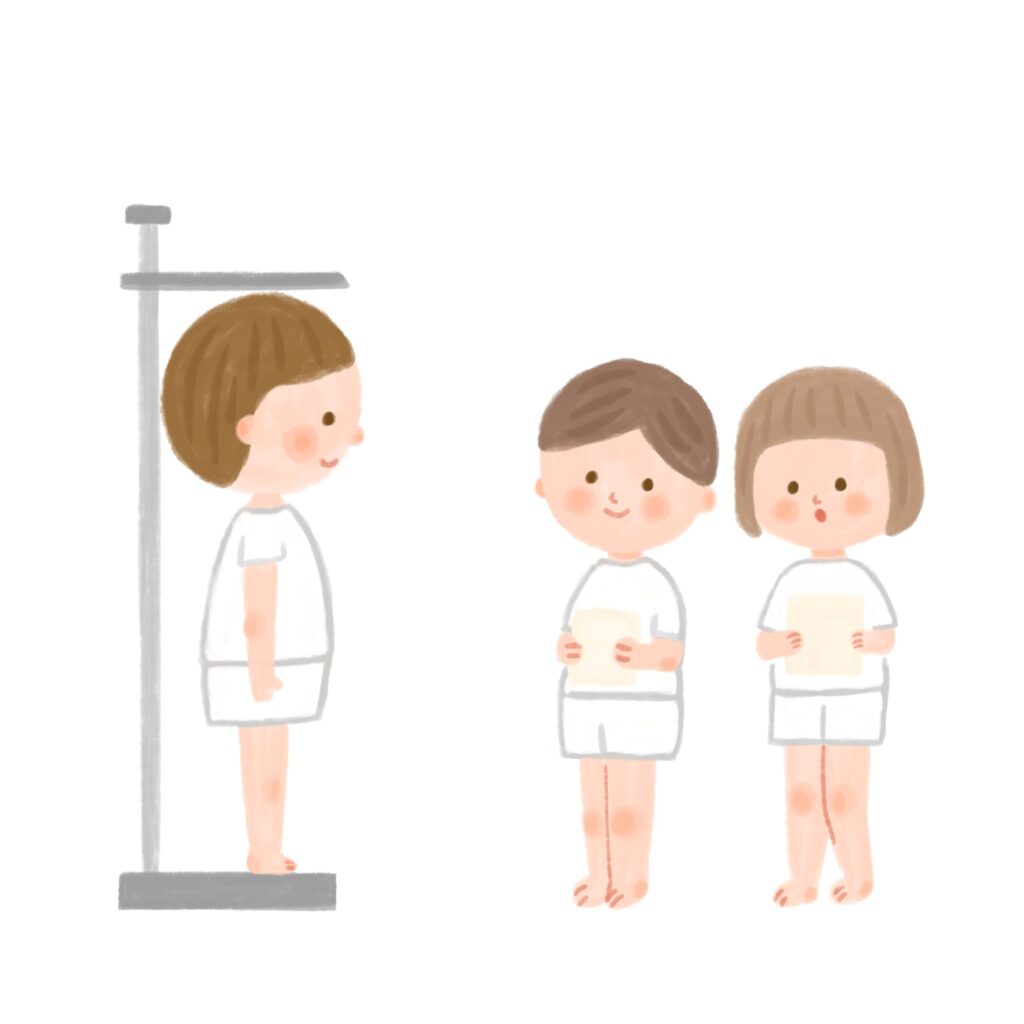
睡眠と成長ホルモンの関係
成長ホルモンは夜22時〜深夜2時の間に多く分泌されます。十分な睡眠時間と早寝早起きを心がけることが大切です。
運動で骨と筋肉を刺激する効果
ジャンプや走る運動は骨への刺激となり、成長を促します。サッカーやバスケットボールなど全身を使う運動が理想的です。
ストレスが成長に与える影響
ストレスが続くと、成長ホルモンの分泌が抑制されます。勉強や習い事だけでなく、遊びやリラックスの時間も子どもには必要です。
まとめ
亜鉛は「見えないけれど、身長を伸ばすために欠かせない栄養素」です。
不足すると成長ホルモンの働きが鈍り、身長の伸びが止まるだけでなく、免疫や集中力にも悪影響が出ます。
牡蠣や牛肉、卵など身近な食材から意識して摂取し、必要に応じて工夫やサプリメントで補いましょう。さらに、睡眠・運動・ストレスケアといった生活習慣を整えることで、子どもの成長を最大限にサポートできます。
「身長を伸ばす=カルシウム」というイメージに加えて、「亜鉛もカギ」という視点をぜひ家庭の食生活に取り入れてみてください。



